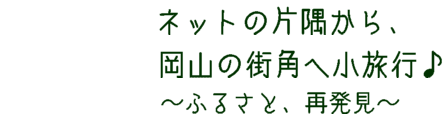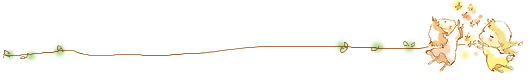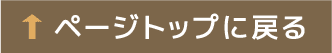地名の由来:倉敷市
倉敷市 概略
市名:倉敷市(Kurashiki)
市の花:フジ
市の木:クスノキ
市の鳥:カワセミ
関連リンク:倉敷市公式HP
地名の由来:地名の由来を紐解く
岡山県で県庁所在地の岡山市に次ぐ規模を誇る都市、倉敷。その地名は、江戸時代に天領(幕府直轄領)として栄え、米の集積地だったため、蔵屋敷が立ち並んでいたことに由来します。
この地名には二つの説があります。一つは、蔵屋敷が転じて「倉敷」になったという説。もう一つは、物資を保管する中継地点を「倉敷地」と呼んでいたことに由来するという説です。いずれにしても、物流の拠点としての倉敷の歴史を色濃く反映しています。
現在、倉敷市では古くから残る白壁の蔵屋敷を保護し、江戸時代から大正期にかけてのレトロな建築物が織りなす美しい景観を形成しています。この一帯は「倉敷美観地区」と呼ばれ、日本の原風景を残す観光地として国内外から多くの人気を集めています。
倉敷と海の深~い関係
かつて倉敷市の周辺は、江戸時代以前は大小の島々が点在する内湾でした。当時の倉敷は、これらの島々を航行する船で大変賑わっていました。
その後、周辺地域の干拓が進められ、現在の陸地の姿へと変貌を遂げました。
そのため、倉敷市のあちこちには、干拓以前の「海」の記憶をとどめる「島」などの名称が付く地名が今も数多く点在しています。
美観地区に鎮座する倉敷の総鎮守、阿智神社の主祭神が、海の神・航海の神として知られる宗像三女神であるのは、こうした倉敷と海の歴史的な繋がりを象徴しています。
水島と倉敷市の合併秘話
現在の倉敷市は、何度かの合併を経て形成されましたが、中でも最も大規模だったのは、旧倉敷市、玉島市、児島市の三市合併です。
この合併により、岡山県南部における岡山市に次ぐ主要都市としての地位を確固たるものにしました。
しかし、実はこ当初から三市が合併を目指していたわけではありません。
水島臨海工業地帯の整備を進める中で、一つの大きな問題が浮上しました。
埋め立てによってできた土地の境界が曖昧だったのです。領有権を巡るトラブルを避けるため、各市が協議を重ねた結果、三市合併という形がとられることになったと言われています。これは、地域の発展のために柔軟な対応が取られた興味深い歴史的背景です。