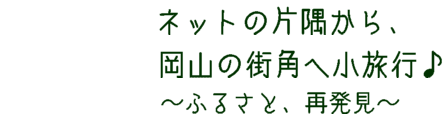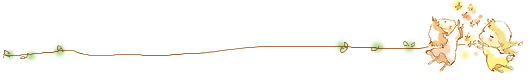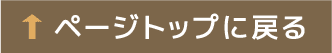【怪談】観音端供養碑の話し
幕末から現代へ伝わる祈りの記憶──笠岡「観音端供養塔」の物語
笠岡市の古城山公園のすぐ下、港の一角にひっそりと佇む石碑があります。
その名は**「観音端供養塔」**。
この碑は、幕末から戦中にかけての世情を今に伝える、歴史ある供養塔です。
かつてこの地は“自殺の名所”だった
1852年、笠岡の西端にある岬「観音端」にこの供養塔は建てられました。というのも当時、近くの古城山の観音堂やその下に広がる海で、自ら命を絶つ人が相次いでいたのです。

正確な人数こそ記録に残っていませんが、あまりの多さに「港や町の活気が失われるほどだった」と伝えられています。
鎮魂のため、町が動いた
この異常事態に危機感を覚えた庄屋や町役人たちは協議を重ね、浅口から僧侶を招き大規模な供養を実施します。そして観音端供養塔を建立しました。
すると不思議なことに、それ以降は自殺者がぴたりと途絶えたといいます。
戦争で失われ、再発見された供養塔
長らく人々に守られてきたこの石碑も、第二次世界大戦中の笠岡港の整備事業の際、土地造成に巻き込まれて行方不明となってしまいます。
しかし1970年、地元の高橋鋳造所が敷地内の工事中に折れた状態の供養塔を偶然発見します。

すぐに補修し、構内に大切に祀りました。
再び“元の地”へ──今に残る祈りの形
後に高橋鋳造所が古城山の斜面整備に伴って移転する際、供養塔はもとの観音端に近い場所へと移されました。
現在では、道路に面した場所で誰もが目にできる形で祀られています。
一度は忘れられた祈りが、再びこの土地に根を下ろした。
この供養塔は、笠岡の人々の心と歴史を今に伝える、静かで力強い証人です。
この石碑には幕末、そして戦時中の世情を物語るエピソードがあります。
「歴史の証人」
この供養碑の解説版では碑を「歴史の証人」と表現しています。
自殺者が多発したのは幕末の政情が不安定な状態だった為だそうです。
現代では幕末と言えば供養碑が建てられた後のペリー来航などの時期を指しますが、それ以前の時期も天保の飢饉やそれに批判的な立場の大塩平八郎の乱の発生、そして幕府の財政再建策も失敗に終わるなど、不安定な時期が続いていました。
そうした時期に自殺者が続いたというのは、当時の政情に将来の不安を感じる人が少なくなかったという事でしょうか。